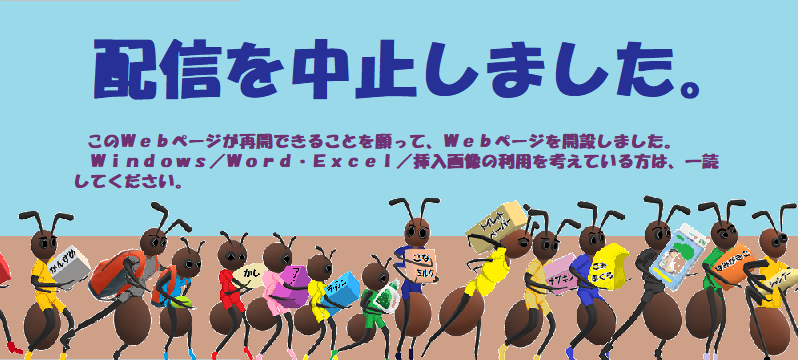配信を中止しました。
このWebページが再開できることを願って、下記Webページを開設しました。
拡散情報は何が正しい?Word・Excelの挿入画像について
Windows/Word・Excel/挿入画像の利用は大丈夫?
Windows/Word・Excel/挿入画像の利用を考えている方は、一読してください。
次記は、閉鎖した、無料ペイント作成絵本「ありと地震」の記載内容の一部です。
早く、再開できるとを願っています。
1 この作品の主旨
(1) Windowsの標準装備で、(無料の)絵本作りに挑戦してみて下さい。
① この絵本の作成には、タッチペン(スタイラスペン)は、使用していません。
② この絵本は、Windows10でも、Windows11でも、3Dペイントが使用できても、3Dペイントが使用できなくても、Windowsの標準装備だけで、ほとんど変わらず、容易に作成できます。
③ この絵本は、ペイントをキャンバスにして、パソコン/Windowsに標準装備されているWordやExcel、ペイントに収納されている3Dモデル、図形、アイコン、3Dライブラリなどの(無料の)画像/ペイントの作画アイテムを選択➝調節➝コピー➝貼り付けの単純作業の繰り返しで作成したものです。(一部画像に写真を用いています。)
④ ですから、絵画経験が乏しく、デッサンの苦手な方でも、素敵な絵本を作りたいという熱い思いがあり、1つ1つのパーツ画像を大切にして作成すれば、素敵な絵本が完成しますので、絵本作りに興味のある方は、是非、Windowsに標準装備されている(無料の)画像/作画アイテムでの絵本作りに挑戦してみて下さい。
(2) この絵本作りの知識を、オリジナルアルバム、各種お知らせ、チラシ、ポスターなどの(無料の)作品作りに利用して下さい。
作者の絵本作りの知識は、作者が過去に旅行や冠婚葬祭などの写真でオリジナルアルバムを作成した経験により習得したものです。
アルバムに写真をあじけなく配置するだけではなく、パソコン/Windowsのペイントを使用して、被写体のその時々の表情や情報を文字にして挿入したり、写真を印象的な大きさや形状に加工したり、効果的な図形を挿入して、オリジナルアルバムを作成した経験によるものです。
絵本作りと、オリジナルアルバムや挿絵や写真の入った人目を引く各種お知らせ、チラシ、ポスターなどの(無料の)作品作りは、共通点が多く、この絵本作りを経験すれば、これらの作品が簡単に作成できます。